SCROLL

2025年に開設25周年をむかえる京都芸術センター。築90年を越える元校舎を拠点に、アーティストによる展示や舞台公演、ワークショップ、トークなど、これまで数々のイベントが開催されてきた。また、アーティストの制作支援活動として、若手アーティストへの制作室の提供や、展示・公演の公募や協働、アーティスト・イン・レジデンスなどにも開設当時から取り組み、京都の芸術文化活動を長年にわたって支えてきた。
そんな京都芸術センター25周年を前に、これまでの歩みをあらためてふりかえるべく、歴代のアートコーディネーター*(以下、AC)が集まる座談会が開催された。
今回集まったのは、初代ACを務めた丸井重樹さん(AC在籍期間:1999〜2002年)、井原麗奈さん(2005〜2007年)、現在もプログラムディレクター*として在籍し、今回の座談会のホストでもある谷竜一さん(2016〜2019年)、そして、遠山きなりさん(2018〜2021年)。
京都芸術センターに眠る膨大な記憶を掘り起こすべく、4名それぞれの年代から見た、芸術センターに関する印象的なトピックスをふりかえっていただいた。
公式の年表には書ききれない、数々の“こぼれ話”から見えてきたのは、時代の変化とともにアップデートを繰り返してきた京都芸術センターの姿。それぞれの視点から見た芸術センターの歩みをふりかえる。
* プログラムディレクターは、事業運営に関わる業務をおこないながら、事業リーダーとして、アートコーディネーターの指導・育成・管理をおこなう。

丸井重樹さん
京都芸術センター初代アートコーディネーターであり、現在はロームシアター京都管理課長を務める。C.T.T.京都事務局、演劇ビギナーズユニットプロデューサー、京都ビエンナーレ事務局、NPO法人京都舞台芸術協会事務局長、京都国際舞台芸術祭(KYOTO EXPERIMENT)事務局などに携わる。また、仕事の傍ら、劇団「ベトナムからの笑い声」の代表兼制作を務め、「ベトナム…」無期限活動停止後に、パフォーマンス企画ユニットTHE GO AND MO’Sを黒川猛と立ち上げ、現在に至るまで代表兼制作を務める。

井原麗奈さん
2005〜2007年に京都芸術センターのアートコーディネーター、その後ピアノ四重奏団アンサンブル・ラロのマネージャーとしてさまざまな分野の催事のマネジメントに携わった。神戸女学院大学大学院 文学研究科博士課程修了、博士(文学)。近代日本と植民地朝鮮の公会堂の設置経緯、運営方法等の比較から文化施設の歴史的意義や公共性について研究している。国立大学法人 静岡大学の専任教員を経て2021年より兵庫県公立大学法人 芸術文化観光専門職大学 講師。近年は指定管理者の評価、パフォーミングアーツの公演評の執筆なども行なっている。
photo by Ichikawa Katsuhiro

谷 竜一さん
京都芸術センター プログラムディレクター。2016年〜2019年に京都芸術センターのアートコーディネーターを務めたのち、京都府地域アートマネージャー(山城地域担当)を経て、2021年より現職。京都芸術センターでは演劇・ダンスを中心に、現代美術、伝統芸能等多岐にわたる事業企画・運営を担当。主な担当事業に KAC Performing Arts Program『シティI・II・III』(2019)、『演劇計画II─戯曲創作─「S/F ─到来しない未来」』(2016-2019)など。また、詩人・演劇作家・「集団:歩行訓練」代表としても活動している。

遠山きなりさん
2018年から2021年までアートコーディネーターとして京都芸術センターに在籍。在籍時は、事業の企画、制作支援事業のほか、コロナ渦の芸術関係者へ向けた補助金窓口対応を担当。その後、奈良県が運営する文化施設・なら歴史芸術文化村の立ち上げに参加。現在は、同施設でアートコーディネーターを務め、アーティストレジデンスの企画・運営などに携わる。
本番公演はおこなわない?
“アーティストのための施設”だった開設当初
― 本日はよろしくお願いします。芸術センターのACの任期は基本的に3年なので、25年前を知るスタッフの方も少なくなっているようです。まずは、開設当初に務めておられた丸井さんからお話をお聞かせください。
丸井さん
僕は、芸術センターの立ち上げ時期である1999年から在籍していました。それこそ、大学を出て数年フリーターをした後に、初めての就職先で。企画の右も左もわからない状態で入ったんですよね。当時の体制は今とは違って、運営委員といわれる事業の方針を決める人の下に企画委員という人がいました。私が担当していた演劇とダンスの事業にはさらにその下で具体的な企画を立案するプロデューサー的な立ち位置の人がいて。僕はその人たちの指示に沿って、業務をしていました。
― 現在の芸術センターにつながるような出来事は、ありましたか?
丸井さん
たくさんあったように思いますけど、記憶に残っている変化でいうと、演劇の本番公演を芸術センターでやりはじめたことでしょうか。今では、センターで舞台公演もおこなっていますが、開設当初は劇場としての機能はもっていなかったんです。伝統芸能公演のシリーズ「継ぐこと・伝えること」や、音楽事業「音楽と市民の広場」などは講堂で上演が行われていましたが、演劇やダンスの本番をフリースペースや講堂で上演するような、小劇場的な使われ方の想定はなかった。あったとしても「試演会」や「(ワークショップの)発表会」でした。つまり、発表や鑑賞の場としてよりも、「つくる場所」であることが中心にあったんですね。そういう意味では、現在よりも「アーティストのための施設」という側面が強かったのかもしれません。
ただ、2000年以降、近鉄アート館や、近鉄劇場・近鉄小劇場、扇町ミュージアムスクエアなど関西周辺の劇場がバタバタと閉館していったんです。
谷さん
私もすごく覚えています。衝撃でしたね。
丸井さん
それまで京都で稽古して、大阪に行って公演をしていた時代。そんな大阪にも劇場がなくなって、京都芸術センターの機能をあらためて問われるような機会だったように思います。そこから、センターでも本番公演を少しずつ充実させていくという流れになっていったように思います。
谷さん
芸術文化をとりまく環境の変化が、センターの機能を変えていったのですね。
京都芸術センター開設、市民の声は?
― 京都芸術センターができた当時、周辺住民や市民からの声はどのようなものだったのでしょうか。
丸井さん
けっこう話題にはなっていましたね。小学校をリノベーションした文化・芸術施設であることと、地域の人たちに馴染みある前田珈琲の店舗が旧1年1組の教室に入っているということ。キャッチーなところから存在を知ってもらったように思います。
― 今では、小学校を改装した施設も多くなりましたが、当時はめずらしかったのかもしれません。
丸井さん
当時、四条烏丸ってビジネス街で。今もそうですけど、室町通も織物の卸問屋さんが軒を連ねている場所で、あまり若い人が来るような街ではなかったんですよね。
それが芸術センターができて、その中に前田珈琲もあって、街の様子が変わっていったなと感じた記憶があります。もともと当時の繁華街だった河原町が、どんどん烏丸の方に寄ってきたというか。おそらく芸術センターだけの効果ではないと思いますけど、確実にその一端を担ってたんじゃないかなという気はしますね。

谷さん
市民の方々のことでいうと、今も大変お世話になっていますが、ボランティアスタッフも当時からあったんですか?
丸井さん
ありましたよ。開設時に200人くらいの応募をいただいて。正直そんなに人が集まると思っていませんでした。
谷さん
今とあまり変わらないくらい集まっていますね……。すごい!
丸井さん
僕もすごく驚きました。こんなにもアートの文脈で一緒に何かを考えたい人や、手を動かしたい人がいるんだと驚いたのをよく覚えています。
そして、ボランティアスタッフのみなさんにはさまざまなことを教えられました。マニュアル作りからシフト制作のところでも……。よくご指摘いただいてました。そこからこうしたらいいのか!と新しい気づきがあったり、ボランティアのいいところと悪いところなど、当時の僕にとっては学びだらけでしたね。
― 印象的な事業という点ではどうでしょうか?
丸井さん
事業の面では、ふたつあって。ひとつは『GEISENN♡W』という芸術センターのACが記事を書く通信紙。制作支援事業(作品創作のために制作室を提供する事業)で制作された作品のレポートを書いて発行していました。通信紙といえば、開設当初から2021年ごろまで発行していた『京都芸術センター通信 明倫art』がみなさんの記憶には新しいかと思うのですが、それとは別に発行していた紙媒体で。『GEISENN♡W』は、我々ACが執筆を担当していたこともあり、あらためて自分たちの仕事のことや立場のことを考えるきっかけとなりました。


丸井さん
もうひとつは、2002年3月に開催された、先駆的・実験的事業『拡散するアジア』。90-00年代の京都の舞台芸術界を語るにあたって欠かせない存在である、杉山準さんと坂本公成さんが企画した舞台芸術の事業です。
海外からの舞台芸術作品といえば、西欧か北米からのものが多かった時期に、アジアに目を向けた舞台芸術の企画でした。演劇は、当時企画委員を務めていただいていた劇作家・松田正隆さんの岸田國士戯曲賞受賞作品「海と日傘」を、日本と韓国の演出家がそれぞれ上演するというものでした。ダンスの企画は企画者である坂本公成さん率いる「Monochrome Circus」のメンバーが中心となってアジア各地を旅してアーティストと出会い、そこでコラボレーションした作品の集大成を上演する「大収穫祭」。香港やシンガポールの劇場関係者を招いてのシンポジウムも開催しました。就任当初から少しずつ準備を進めていて、韓国やシンガポールに出向いたり、全く英語ができないにも関わらず海外のゲストとメールをやり取りしたり、3年がかりで大変でしたけど、勉強になった企画でした。

前例のない施設を運営すること
アップデートを重ねた25年
― 続いて、井原さん。井原さんは、2005年〜2007年のACですが、在籍時に印象的だったことはありますか。
井原さん
記憶に残っていることばかりですね。特に感じていたのは、前例のない施設を運営していくことの難しさです。今は改善されていると聞き安心していますが、芸術センターがまだ5年目だった当時、労働環境はあまり良いものとは言えない状況でした。私も社会人1年目にしていきなり現場に送り出され、右も左もわからないまま、なんとか乗り切っていたのを覚えています。
谷さん
芸術センターをどのように運営していくかというのは、今後も考えていかなければいけない課題のひとつです。
井原さん
運営組織の構造もこれまでに大きな見直しが図られてきたように思います。現在はプログラムディレクターという役割の人がいますが、私がいたころは、事務局長とACをつなぐ中間的な立場の人がおらず、事務局長の直下にACがいるという構図でした。事務局次長や係長という職の人もいましたが、みなさん京都市からの出向職なのと、もともと芸術関係の方ではないということもあり、そこのハンドリングもなかなか大変で……。
このように、当時は毎日かなりバタバタしていました。任期が3年で入れ替わっていくので、私のいたころは土台となる考え方がまだ定着しておらず、試行錯誤の日々でしたね。
谷さん
だいぶ改善はされましたが、今もかなり試行錯誤の日々です。
井原さん
アートセンターって今では他都市でも見られますが、京都芸術センターが全国的にかなり最初にできたアートセンターだったんです。先行事例もなかったので、相当手探りの運営だったように思います。
― そうした経験を積み重ねながら、アップデートがされてきたのですね。
井原さん
そんな状況があっても、今でもこうして私がアカデミアとしてアートの業界にいられるのは、やはり当時、芸術センターの事業を通して出会ったいろんなアーティストの方々によくしてもらったことで、アーティストとアートの愛し方を学んだからだと思っています。ACたちがアーティストとアートを愛しみ、また逆に愛されてもいる側面をフルで発信できるように、運営は今後もよりよくあってほしいです。
アート・舞台芸術・文芸…
領域を横断し、視点を変えた楽しみを
― 印象的な事業という点はいかがでしょうか。
井原さん
記憶に残る事業はいくつかあります。例えば、文芸系の事業の『文芸てくてく』。私の任期終了と同時に無くなった事業なんですが、芸術センターを離れた今でもとても記憶に残っています。
井原さん
京都市美術館(京都市京セラ美術館)のコレクション展を吟行し、気に入った作品を俳句に読むというワークショップをおこなったのですが、普段美術館にはあまり行かない文芸系の人たちが新鮮な表情で楽しまれていたのを覚えています。こういった視点を変えて、ジャンルを横断した楽しみ方の提案をできるのが、京都芸術センターの役割だったのかもしれないなと今さらながらに思います。
谷さん
プロジェクトは続けていきたいけど、いろんな背景があってなくなってしまうこともあって、もどかしいですよね。
井原さん
そうですね。ただ、センターで企画した事業が、その後の京都のアートシーンを発展させた事例も見てきました。
特に広がりのあるものだったのが、『京都芸術センターセレクション』や『演劇計画』などの舞台芸術系の事業。その事業で当時活躍されていた丸井さんや橋本裕介さんがそれらの事業を、今年で15周年をむかえる国際的な舞台芸術祭「京都国際舞台芸術祭(KYOTO EXPERIMENT)」につなげてくださっていて。そう思うとちょっと感慨深いものがありますね。

実験精神でアーティストと併走すること
― 続いて、谷さん。谷さんがACとして在籍していたのは、2016年から2019年、そしてプログラムディレクターとして2021年から現在まで在籍しています。ふたつの時代から芸術センターを見てきて、印象的だったことはありますか。
谷さん
芸術センターにかぎらず、京都のアートシーンに比較的長く関わっているからこそ感じているのは、この土地ならではの特徴みたいなものです。
僕は少しイレギュラーかもしれませんが、京都芸術センターのコーディネーターの前にはアーティストとしても活動していたので、京都の人と人の縁や、いい意味での狭さみたいなものを感じていました。たとえば、あのときはあの肩書きで出会ったのに、別の場所でまた別の肩書きの人として出会うみたいなことが多くて。いろんな立場での関わり合いができるというのは、京都のアートシーンならではのおもしろさかもしれませんね。
― なるほど。芸術センターでもそのような出来事はあったのでしょうか。
谷さん
ボランティアで関わってくれた方が実は作家さんで、その後何かの公募事業で応募してくれたり、職人さんだったりしたことも。京都芸術センターを拠点として、そういった人の多面性のようなものに出会えることや、その人のいろんな側面を引き出し、長く付き合っていくこともセンターの役割のひとつであるように感じます。
― ボランティアの募集や公募事業が、そのような活動の促進にもつながっているように思います。ほかに印象的だったことはありますか?
谷さん
井原さんの話にも挙がっていましたが『演劇計画』は印象的な事業でした。僕は『演劇計画Ⅱ「S/F―到来しない未来」』を担当したのですが、劇作家の育成にフォーカスした事業で。2人の劇作家と、それぞれ3年かけて1本の戯曲を創作するという長大なプロジェクトでした。最初聞いたときは、3年も劇作家を拘束する仕事を、しかも当時新任だった僕に任せるとは、なかなかチャレンジングな施設だなと思った記憶があります(笑)。

谷さん
以降2019年の完成まで、色々なトークを企画したり、取材を設計したり、戯曲をもとにした展覧会をやったりして、劇作家2名をたいそう困らせたと思うのですが、改稿されていく戯曲を読むのは、とても楽しかったですし、僕自身も成長させてもらいました。
芸術センターの実験精神と、アーティストとの併走を重んじる性質が、よくあらわれた事業だったと思います。こういう無茶な事業はまたやりたいですね。
― 実験精神とアーティストとの併走。芸術センターをまさに表す言葉のように思います。
コロナ禍を経て
新たに見えてきた芸術センターの役割
― 駆け足で、ほんの一部を振り返ってきましたが、最後は遠山さん。在籍時に印象的だったことはありますか?
遠山さん
ひとつ、時代の流れとしてアーティストにとって何をしたら成功なのか、わかりづらくなってきているなというのは感じていました。いい作品を作ったら直ちに売れるというような時代でもなくなっていて。
― 芸術や作品のあり方もどんどん多様化してきています。
遠山さん
そんななか、私が入る少し前からはじまったのが「Co-program」という公募事業。いくつかカテゴリがあるうちのひとつが、展示や公演を成果としない実験的な取り組みの募集です。比較的小規模な企画やアイデア段階でも応募できるので、若手アーティストによる幅広い活動が増えてきたように感じていました。これからも、どんどん新しい芸術や作品のあり方が出てくるのではないかと楽しみにしています。

― 一方、遠山さんの在籍期間の半分は、コロナ禍でした。今まで積み重ねてきた、京都芸術センターのあり方が全く通用しない数年だったと思います。
遠山さん
コロナでいろんな事業がストップして、新たにはじまったのが、京都市による芸術関係者への補助金の申請対応業務や、芸術関係者の現状把握のためのアンケートでした。センターも2ヶ月間ぐらいは完全に休館し、その後も様子を見ながら時間短縮などで開館していました。補助金対応やアンケートはその後、芸術関係者に向けた相談窓口「京都市文化芸術総合相談窓口(KACCO)」につながり、今も続いていますよね。

谷さん
アーティストと作品をつくって発表するというそれまでの役割にくわえて、補助金対応や相談窓口といった作家の支援となるインフラ的な事業が立ち上がったんですね。
遠山さん
そうなんです。当時、意外にも京都市にそういったことができるところは多くはなかったようで。芸術家の横のつながりを生み出すだけではなく、芸術家個人に還元するという意味合いにおいても大きな出来事だったと思います。なんとなく大きな流れとして、それまで、制作・発表の場であった芸術センターが、情報収集・発信をおこない、人々が交流する拠点にシフトする転換点だったのではと今は振り返っています。
― 当時のアーティストたちの声はどのようなものだったのでしょうか?
遠山さん
臨時休館が終わって再開した後にも、アーティストに貸し出しをしている制作室の利用人数や時間帯を制限した期間があったんです。その際に利用アーティストから寄せられた、「制作室を使いたい」「制作の場がなくなって本当に困る」、という切実な声は本当に印象的でした。
― あらためて、アーティストにとって、制作環境の整備やサポートがどれだけ大きな意味をもつかを考えさせられますね。
遠山さん
そんな通常通りの作品制作や発表ができなくなったなかでも、その状況を反映した作品をアーティストと協働して制作したり、延期公演もそれを発展させたものとなったり。
劇団速度(現在はレトロニムへ改名)という団体による演劇公演は、まさに最初の休館がはじまるころに予定されていて延期となりました。その際、公演のためにおさえていた会場と芸術センター近隣の道端などを舞台に映像作品を制作し、経緯をまとめたテキストとともにオンラインで発表を行いました。そしてちょうど1年後、あらためて観客を集めて開催した公演は、映像作品をとおして深められたアイデアが反映されていました。状況に応じたしなやかな対応や創造性は、今でも印象深く感じています。
谷さん
芸術センターの20周年事業もコロナ禍でしたもんね。
遠山さん
コロナ禍で迎えた20周年は、「誰もが歳をとる」ということに対して向き合うべく、「We Age」というテーマで事業を企画しました。
当時は感染防止のため、会場面積に対しての収容人数が厳しく定められていました。そのなかで出てきたアイデアが、舞台と客席を別の会場にして、客席でライブビューイングをするというもの。でも単にライブビューイングするのでは一方通行になって、舞台ならではのライブ感に欠ける。そこで、ステージのぐるりに観客数分の電飾付きサーキュレーターを設置し、1台につき1つのスイッチを客席につなげました。観客は、心が動いた瞬間にスイッチを押し、自分専用のサーキュレーターで風を送り、電飾を点灯することで出演者に意思表示ができます。別会場といっても、同じ場所の1階と2階に位置することを活かして、あえて有線ケーブルを物理的につなぐことで、臨場感の演出も試みました。



― 芸術センター全体としても、コロナ以降大きな変化が必要とされたように感じます。コロナ禍から現在も在籍する谷さんから見て、いかがでしょうか。
谷さん
特に、演劇やダンスなどのパフォーミングアーツというジャンルの多くは、大勢が同じ場所に集まって観ることを前提に作っているものです。コロナ期間を通じて、人が集まることは常に何かしらのリスクがついて回るということについてあらためて認識させられましたね。
― オンラインツールの活用も進んだ今、集まることの意味が問われているようにも感じます。
谷さん
そうなんです。集まらなくてもおもしろさを享受できる環境になっているなか、あえて集まる意味ってなんだろうと。コロナが比較的落ち着いてからも、ただそのままもとに戻すのではなく、せっかくなら集まることのおもしろさを生かした企画をしようという意識が育てられました。
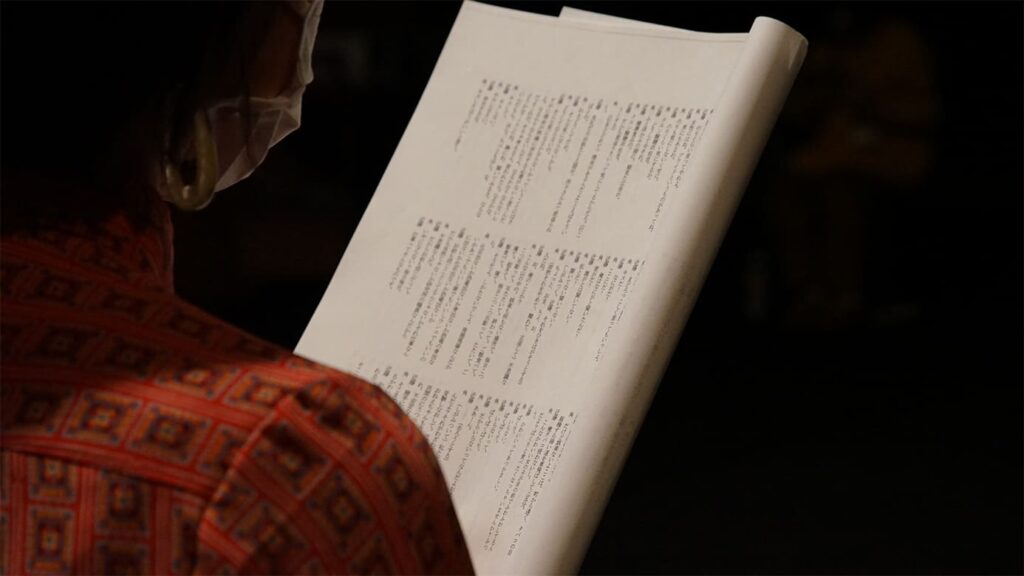

― 4名の視点で芸術センターの歩みをふりかえってきました。あらためて、みなさんいかがでしょうか。
丸井さん
初代の制作支援事業担当者ですが、数年前から再び利用する側、つまり制作室使用者として京都芸術センターに通っています。オープン当時と比べるといろいろなことが変わってきたなと感じますけど、20年以上経って、時代の要請に伴って京都芸術センターの役割自体も、アーティストたちの意識も変わっているので、その事自体は受け止めて行かねばなと思っています。
むしろ、同じところに留まらない「芸術文化を生み出す坩堝」であり、「これまでにない芸術文化の創造の砦になるために絶えざる運営の見直しと新システムの構築を追求していく」(運営趣旨書より)場所であり続けることを願っています。
井原さん
今回あらためて京都芸術センターと自分が関わった事業、自分自身のAC時代を俯瞰した時に、20年を経て、いい意味でも悪い意味でも、変わったところと変わらないところがあるなと感じました。全国的に類似施設が増えていくなかで、継続性や発信力を考えた時に、京都芸術センターの独自性がより強調されていくべきだろうなと思います。
今年の「Co-program」にはかつての自分のゼミ生が応募した企画が採用され、個人的には感慨深いものがありました。若いキュレーターやアーティストが、京都芸術センターに魅力を感じてくれたことをありがたく、うれしく思うと同時に、これからもみなさんに選ばれる文化施設であってほしいですね。
遠山さん
丸井さんがおっしゃっていた当初の「アーティストのための施設」という性格は、その後も芸術センターの根底にあり続けていると感じました。元ACのみなさんの姿勢にも不思議と共通するものがあるのは、これもひとつ大きいのかもしれないと思います。
私も芸術センターでの経験や考え方が、完全に今の仕事のベースになっています。このように全国各地にいる元ACの中に残っているものが多くあって、現在の芸術センターに直接現れていることだけでは測りきれない存在感があるなと今回実感しました。
谷さん
今回は僕がホストになったこともあり、比較的パフォーミングアーツに多く携わってきたACに集まっていただきましたが、時代や環境など時々の状況に応じてめまぐるしくアップデートしてきた姿がやはり印象的でした。
それと同時に、京都芸術センターらしさとはなんだろうとあらためて考えていたのですが、「こういうことをやってみてもいいんじゃないか」という態度そのものに、並走し、翻弄されている姿がひとつ、らしさとも言えるのかもしれません。働き方、考え方、作り方の変容を迫られるようになった今、劇場でも美術館でも博物館でもない、アートセンターという自由度の高い場所であるからこそ、当初のコンセプトや“らしさ”を守りつつ、アーティストや市民とともに考え、変化していく姿勢を持ち続けたいですね。
また、ファインアーツや伝統芸能など他分野のACが集まると、また違った時代の動きのようなものが見えてくるかもしれないので、また今後もこのような機会を持ちたいです。
― 今日はありがとうございました。
歴代アートコーディネーターがふりかえる京都芸術センターのこれまで vol.02
<credit(敬称略)>
企画編集:合同会社バンクトゥ、わかめかのこ/執筆:わかめかのこ/写真提供:丸井重樹、井原麗奈、谷 竜一、遠山きなり、京都芸術センター